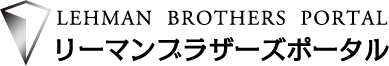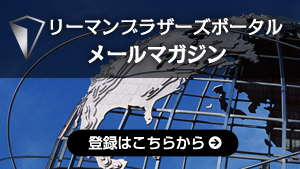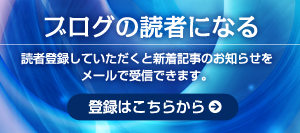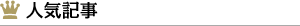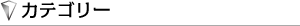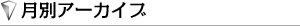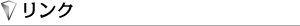【素晴らしい】国立博物館 本館にて【おすすめ】
東館を出て本館に入っていった。

日本の歴史と世界の歴史の流れが比較されていた。中国の戦国時代は紀元前5世紀、日本は16世紀、実に2000年もの差がある。如何に中国が先進国であり続けたかがわかる。

埴輪の土偶が実に躍動感があって素晴らしい。どわぁつと動きが表現されている。

青銅の祭器と埴輪。

花見をする人たち。

仏像に囲まれた仏像。

水墨画。実に枯れた色合いが渋さを引き立てている。白と黒だけでこれほどに高低感、奥行き、広がりを表現できるとはすばらしい。禅の世界観が余すことなく表現されていて、この絵の前に立つだけで気絶しそうになる。

釜。茶の湯で使えば実に味わい深い事だろう。茶を楽しみ、会話を楽しみ、部屋を楽しみ、そして茶器を楽しむ。柔らかな丸みと漆黒の黒、ザラりとした表面が光を吸い込みながら、しっとりと黒く、触れば鉄板のごとく、茶器の訴える波動がジュウジュウと伝わってきそうな作品である。

耳かきのごとき茶杓。静かに、滑らかに磨き上げられた茶杓のカーブが柔らかく抹茶を掬い取り、湯気の立ち込める茶室にて、抹茶が静かに茶器に注がれる。その柔らかさが茶杓の向こうに見えてくる。

薙刀と言えば坊主。坊主と言えば信長の野望。

実に楽しそうに花見している。いつの時代も花見の楽しさは変わらない。

高貴な人々は糞重い服を着て歩き回っていたのだろうが、肩がこるに違いない。

おしゃれは我慢、というのは何年たっても変わらない。

こういう顔の女性はいるなーなんて思いながらしげしげと眺めた。

みんな大好き大飛出。

江戸時代、隅田川の桜。

そして仏像。

躍動感あふれる彫刻

漆は日本が誇る世界一のペイントである。色合いの渋さ、光を吸い込むような深み、スムーズな艶やかさ、柔らかな手触り。。。

日本全国に窯がある。

織部焼。

そして再び大飛出もどき。

能面はなぜこんなに恐いのだろう。

こ・・・これは漫画太郎先生の地獄甲子園では。。。


こ・・・これは会社のお局さんでは。。。

こ・・・これは鬼嫁?

こ・・・怖ぇえ

真一文字とはこのこと。

また真一文字。

アイヌの人達の道具。

アイヌの服。

アイヌの人。

黒曜石。

まだまだ続く。平成館へ。

土偶が並ぶ。おもむろに並んでいるが、こいつら重要文化財のオンパレード。

ふう・・・
いい・・・
実にいい・・・
ここだけで1週間くらいは見れる。いつまでも見ていたい。歴史の向こうに見える果てしない世界に思いを馳せると、当時の人達の生活が生き生きと見えてくるようである。
つづく
大企業に勤務するサラリーマンで、M&Aを手がけたり、世界を飛び回ったりしている。ぬるま湯に浸かって、飼い慣らされているサラリーマンが大嫌い。会社と契約関係にあるプロとしての自覚を持ち、日々ハイパフォーマンスの極みを目指している。歴史を学ぶことは未来を知ること、を掲げてしばしば世界を旅している。最近は独立して生きる力を身に付けるべく、資産運用に精を出している。好きな言葉 「人生の本舞台は常に将来に在り」
■関連記事
バンコクからシェムリアプへ AM4:30起き、AM5:30、バンコクから、カンボジアでアンコールワットのある街、シェムリアプを目指す一日。。。 バンコクの拠点駅、ファランボーン駅から、カンボジア国境近... 続きを読む »
第二次世界大戦の時代、ヒトラーがユダヤ人の排斥を打ち出し、人々の支持を集めた。 現代のドイツはヒトラー1人を極悪人のように仕立てているが、ヒトラーは革命を起こしたわけでも、暴力で政権をとったわけでもな... 続きを読む »
心理学者アドラーの哲学を、哲学者と凡人の対話として分かりやすくまとめた本。取引先から進められて読んでみたがなかなか面白く、色々な人間関係の悩みとか、ふっと晴れるような気がする一冊だった。 書籍名:『嫌... 続きを読む »
ネスレ名誉会長が後任のCEOや役員陣、社員や経営に携わる・若しくは志す人々に自らの経営哲学を伝えるべく書いた本を読んだ。 著者名:ネスレ名誉会長 ヘルムート・マウハー 岸伸久訳 出版日:2009年4月... 続きを読む »
毎年12月になると、街はイルミネーションに覆われ、恋人たちが街中に繰り出す。 ホテルは満室になり、フレンチレストランは予約が取れず、ケーキが飛ぶように売れる。 この騒ぎは一体なんだろうか。と誰しも思う... 続きを読む »