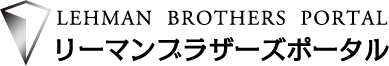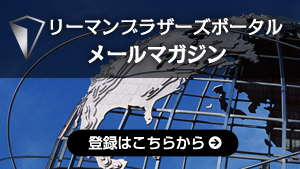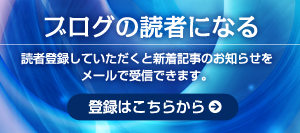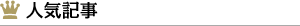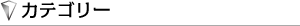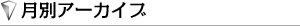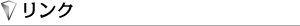『テスコの経営哲学を10の言葉で語る』~企業の成長とともに学んだこと~
英国にあるありふれた小売業の一つに過ぎなかったテスコを、英国最大の小売業に育て上げ、世界展開を強力に推し進めたテリー・リーヒ氏の著作。稀代の経営者の言葉に触れたいと思い読んでみた。
書籍名:『テスコの経営哲学を10の言葉で語る』~企業の成長とともに学んだこと~
著者名:テスコ元CEOテリー・リーヒ著 矢矧晴彦訳
出版日:2014年2月
出版社:ダイヤモンド社
評価:★★★★☆
一般的にこういう本は訳がひどく、著者の本意がなかなか伝わらない文章になっている事が多いが、本書は相当洗練された文章にまとまっており、訳者の流通業に対する理解と翻訳力の高さに驚かされる。
著者が掲げる10の言葉は、真実、ロイヤルティ、勇気、価値観、行動、バランス、シンプル、リーン、競う、信頼。この中でも特に「真実」こそ著者が最も重視しているものだろう。
テスコは何のために存在しているのか、顧客は何を求めているのか、今下そうとしている決断は本当に正しいか、等、全て真実があってこそ判断がつくものである。企業で働くと往々にして、ありふれた真実に目が届かず、目の前にある虚構に惑わされてしまうものだが、著者は真実に目を向ける事の大切さを強調する。言い換えれば、物事の本質とは何かを追及する姿勢が重要と言っているともいえる。
例えば、○○が売れるという噂に乗って物を陳列する事は正しいか、肉コーナーに焼肉のタレを置くことは正しいか、判断が必要になったとする。なんとなく正しいと思う事も、それは想像にすぎず、良かれと思って行った取り組みの答えは在庫の山になって返ってくる。
真実を解き明かすには購買データが重要であり、同氏はデータ入手ツールとしてのクラブカード導入とそのデータの分析に注力していった。得た情報を基に、ロイヤルカスタマー(テスコが好きで「忠誠心高く」テスコで購買する顧客)の囲い込みを徹底した。
巷でもこのクラブカード展開によってテスコは急成長を遂げたと言われている。本書を読了して改めてわかる事は、小売業にとっては顧客が全てであるという事だ。顧客が何を欲しているか、という真実を解き明かす為に、テスコはクラブカードを創りその分析を通じてロイヤルカスタマーを生み売上増加に結び付けていった。
当時クラブカードの導入は、他小売業がまったく警戒心を持たない程に、未知で、大きなリターンを期待できないであろう取組みだった。そんな時代にテスコは「勇気」をもって「行動」していった。その行動を起こす前提には誰よりも一生懸命にお客様の為に努力するという「価値観」が有り、それを従業員に浸透させていたからこそ行動できたのである。
行動する上で重要なポイントとして同氏はウォルマート創業者であるサム・ウォルトンの言葉を借りて、明確な決定、シンプルなプロセス、役割の定義、強力なシステム、そして規律、が大切と述べている。
同氏が挙げている10の言葉は、1つ1つを本当の意味で理解し、実践する事は容易ではなく、だからこそ同氏がテスコのトップに君臨し、急速な成長をけん引できたのだろう。それが本書を読むとよく理解でき、流通業に携わる人間として、またあらゆるビジネスに普遍的な真実を知れる一冊である。
大企業に勤務するサラリーマンで、M&Aを手がけたり、世界を飛び回ったりしている。ぬるま湯に浸かって、飼い慣らされているサラリーマンが大嫌い。会社と契約関係にあるプロとしての自覚を持ち、日々ハイパフォーマンスの極みを目指している。歴史を学ぶことは未来を知ること、を掲げてしばしば世界を旅している。最近は独立して生きる力を身に付けるべく、資産運用に精を出している。好きな言葉 「人生の本舞台は常に将来に在り」
■関連記事
ある日新幹線に乗って一杯やっていた(この日はたまたまグリーン車に乗っていた)。崎陽軒のシウマイを食べて、弁当を食って、ハイボールを飲んでいい気持ちになり、Wedgeを読みながらリラックスしていた。 新... 続きを読む »
地上波で流れているものの中では、久しぶりと言っていい。 凄いものを見た。 1月27日に放送されたバラエティ番組「坂上探検隊」(フジテレビ系)で、狩野英考が自撮り棒をもって野生のライオンに近づき、写真を... 続きを読む »
1日目:成田からデリーへ 成田からデリー行きのJALに乗る。今回もコストを抑えてエコノミーでの旅となったが、JALが機材を新しくしており、ANA以上に快適な事に驚きながら、空の旅を楽しんだ。 私は40... 続きを読む »
都内で働く高給サラリーマンの中には東京カレンダーを日常的に見ているという人も多いだろう。ある人は、あまりに読みすぎて時間をむしりとられるので、アプリを削除したと言っていた。 参考例:シバユカ 最終回:... 続きを読む »
少し古いが牛角でおなじみのレックスHDを売上高3,900億円の一大外食チェーンに成長させた西山氏の手記を読んだので、その表を記す。 書籍名:『想い』~三茶の焼肉、世界をめざす~ 著者名:レックス・ホー... 続きを読む »